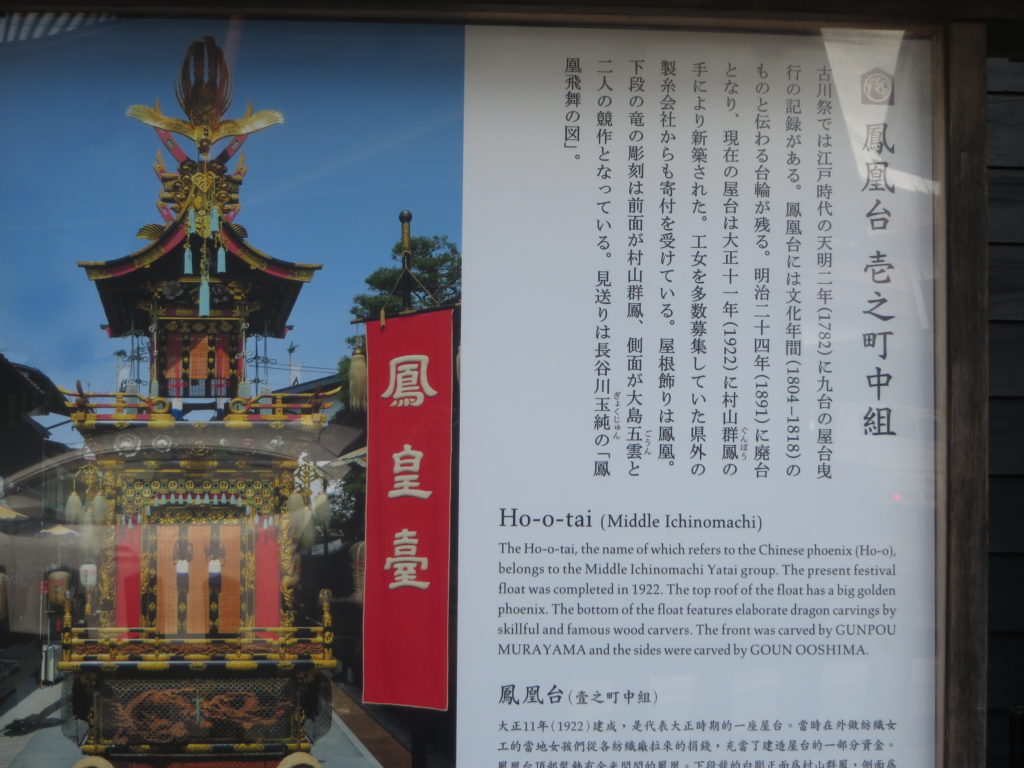沖縄から戻りました。今回は「復帰50周年特別企画」の講演に招かれました。テーマは「私と沖縄の50年」ということで、これまでの沖縄とのご縁について話させていただきました。
そしてパネルディスカッションでは「沖縄(うちなー)女性の歩んだ道」をテーマにそれぞれの分野で活動をなさってこられた4名のパネリストからは看護の現場から、また一日7万食余りの給食を県内のこども園、小中学校へ提供してきた”食の現場”から、また青少年育成のため尽力された方、離島(八重山など)教育現場で活躍された方々のお話しでした。
皆さん私と同世代。大変なご苦労がある中、明るく前向きに歩んでいらしたお話しには私自身励まされました。会場には30代から90代までの会員の方々200名あまりの方でいっぱいでした。
熱気あふれる会場で私はこのような話をさせていただきました。
「女性の翼」が今年40周年をむかえられたこと、本当におめでとうございます。
男女共同参画社会との実現への寄与を目的に、「女性の翼」はこれまで、さまざまな研修会を開き、女性の社会進出を促進する活動を地道に続けられてきました。
国内のみならず、海外セミナーも定期的に行い、そこで感じたこと、学んだことを力に変え、着実に沖縄で実践なさってきたこと、沖縄の女性の底力あってのことだと、深く感じております。
私はこれまで、職業は旅人かと思うほど、多くの土地を旅してきました。心惹かれ、何度も繰り返し、お訪ねしている土地もたくさんございます。
けれど、沖縄ほど魅力を感じる土地はほかにありません。
沖縄に来るたびに、第二の故郷に戻ってきたかのような安堵感を覚えます。ああ、ここに帰ってきたと。私がはじめて沖縄に降り立ったのは、まだ返還前のパスポートが必要な時代でした。そのご縁を結んでくれたのは、民芸運動の創始者・柳宗悦氏の本でした。
柳氏は昭和13年に沖縄を訪ねられたのですが、そのときの感動を「沖縄は自分が思い描いた民芸の理想郷「美の王国」だと綴っていらっしゃったのです。
民芸が提唱する用の美、無名の人が作る美しい沖縄の道具をこの目で見たいということ。それが第一の目的でしたが、回数を重ねるごとに、沖縄の女性にどんどん惹かれていく自分に気づかされました。
決して忘れられないことのひとつが、故・与那嶺貞さんとの出会いでした。
ご存知のように、貞さんは、琉球王府の美の象徴であり、民族の誇りでもある花織を、復元した女性です。民芸を訪ねる中で、貞さんに出会えたことは、幸運としかいいようのないものであり、貞さんと過ごした時間は今も鮮やかに記憶に刻まれています。
出会って以来、ことあるごとに、私は貞さんの元を訪ねさせていただきました。貞さんの人生は、多くの沖縄の女性と同様、過酷なものでした。第二次世界大戦で夫をなくし、自分は銃火の中を三人の子どもを抱えて逃げまわり、終戦後、女手ひとつで三人の子どもを育てられました。
その子育ても終わった55歳のときに、貞さんは古い花織のちゃんちゃんこに出会い、その復元を決意なさんたんですね。琉球王府の御用布であったにもかかわらず、工程の複雑さ、煩雑さから、伝統が途絶えてしまった花織を、貞さんは幾多の苦労を経て復元し、人間国宝となられました。
貞さんが織った花織は、何本もの糸を用い、花が浮いたような美しさです。驚くほど軽く、肌触りは限りなく優しいんです。貞さんのその着物は、私の宝物です。
貞さんは「女の人生はザリガナ。だからザリガナ サバチ ヌヌナスル イナグでないとね」とよくおっしゃっていました。
ザリガナとは沖縄の言葉で、もつれた糸をほぐすこと。
女の人生はもつれた糸をほぐすこと。今日、ほぐせなかったら、10日、1年、いやもっとかかっても根気よくほぐしてこそ、美しい花織を織ることができる……。
貞さんのこの言葉は、みなさま、沖縄の女性の本質を表しているのではないでしょうか。「女性の翼」の力の根源ではないでしょうか。根気よく糸をほぐすためには、辛抱強さと優しさが必要です。ほぐした後にどんな織物を織ろうかと、未来へつなぐ希望も兼ね備えていなくてはなりません。辛抱強さと優しさ、希望を持ち合わせている沖縄の女性、「女性の翼」こそが、21世紀のよりよい社会を作る大きな力となると私は信じています。
とはいえ、今も沖縄には、さまざまな問題が山積しています。
沖縄は、先の戦争で、日本本土防衛の最後の砦となりました。
約3カ月にわたって日米両軍による激しい戦闘が繰り広げられ、日米双方で20万人もが命を落としました。県民も約4人に1人が犠牲になりました。軍人よりも民間人のほうに多くの犠牲が出た悲惨な戦いでした。
戦後は、アメリカ統治下となり、琉球政府は三権分立の形をとっていても、統治者と被統治者の別があり、軍事優先の政策に翻弄されました。
そして1972年5月、27年間に及んだアメリカ統治が終わりを告げ、沖縄は日本に復帰しました。
それから50年。今年、返還50周年を迎えました。
今、青い空と海、穏やかなで明るい人々に心惹かれ、沖縄は多くの観光客が訪れる場所となっています。しかし日本復帰から50年が経った今なお、変わらない問題もあります。「二度と戦争はしない。してはいけない」という決意がどこの人より強い沖縄の、その国道の脇には大きな長いフェンスが渡され、町が基地で分断されている状況が今も続いているのです。
このことを私たちは決して忘れるわけにはいきません。
また2年半に渡る新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請のために、沖縄の観光産業は大打撃を受け、先が見えない状況が続きました。こうした中で増えるもののひとつが、子どもや女性に向けられる暴力です。行き場のないフラストレーションが弱者に向かってしまうんですね。
沖縄でも残念なことにDV被害者が増えています。また、近年、困窮するシングルマザーも増えてきました。
「女性の翼」は、今すぐ、待ったなしでサポートを必要としているこうした女性たちのために真っ先に立ち上がって下さっています。
「あなたの笑顔が私の笑顔」という言葉を掲げ、「女性の翼OK基金」を創設し、行政の制度では間に合わない緊急の対応や、施設から自立するときの一時金で、大変な状況にある女性たちを支え、応援して下さっています。
「女性の翼」の会員は30歳台から90代まで、250 名もの正会員がおり、県内市町村の女性議員の多くも会員というのも心強い点です。男女共同参画が提唱されて久しい今でも、出産、子育て、介護など、人生の節目節目で立ち止まることをよぎなくされる女性も少なくありません。
それでも、「女性の翼」が40年に渡り、女性の心をつなぎ、手を握り、ネットワークを作り上げ、活動を広げてきたというのは、会員ひとりひとりの思いの深さ、確かさ、また包容力や気持ちの温かさあってこそだと思います。
女性も男性も、自分らしく「人間らしく」生き生きと暮らせる沖縄を作っていくためには、これからますます「女性の翼」の活動が必要です。
みなさんのこれまでの努力に感謝し、敬意を表すと共に、これからもがんばってくださいますようにとエールを送らせて下さい。
私も微力ながら、沖縄のために活動を続けるつもりです。
ひとつ私が心に期しているのは、首里城の再建のために、全国の皆さんに沖縄の職人の素晴らしさをいま一度知ってもらおうということです。
首里城の建物、そして収蔵品や復元品にいたるまで、琉球の粋と心が詰まっていました。復元するには職人さんがなくてはなりません。
伝統を受け継ぐ職人たちも育ってもらわなくてはなりません。
やちむんや琉球ガラス、漆器、芭蕉布や花織など各地の織物……。
この悲しい出来事を機に、本土の人にも沖縄の伝統工芸を知ってもらうために、私もまた発信を続けて参りたいと思っております。
先日は主婦の友社の雑誌「ゆうゆう」との企画で、松田米司さんのやちむん八寸皿をご紹介し、読者さんを中心に通信販売もすることができました。こうして少しずつではありますが、できることを今後も進めていくつもりです。
そして、何より、これからも私は沖縄の女性たちとともに歩んでまいりたい。
皆さんの仲間でいたいと思っております。
本日はありがとうございました。

恩納村の会場から那覇空港に向う途中にある道の駅に寄り ゴーヤと海ぶどうを買い、松田米司さんの器に”ソーメンチャンプルとゴーヤチャンプル”を作りいただきました。この器は八寸なので、カレーでもパスタでも何にでも使いやすいです。
年明けの釜出しに合わせて”ゆうゆう”(主婦の友社)の1月号(12月1日発売)、2月号(12月28日発売)で お求めいただけます。